| TOP | 美ヶ原の味 | 山辺ぶどう | 山麓の民俗 | 森の現況 | エコツ−リズム | グリ−ンツ−リズム | |
| エコマップ |
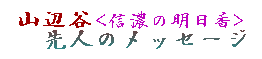 |
和田峠の黒曜石 長野県では約350ヵ所の旧石器時代遺跡が確認されている。全国の約十パ−セントである。 これは、当時の信州が気候温暖で、風土が狩猟生活に合っていたこと、生活道具をつくる黒曜石があったからである。 ビ−ナスラインの和田峠付近は本州最大の黒曜石産地である。 黒曜石の交易範囲は想像以上にひろく、関東・中部一円に運ばれている更に遠く青森県下で和田峠産の黒曜石が確認された記事を見た。 和田峠は山辺に近いので、運んできた黒曜石を加工した場所がある。 今も畑から切りくずがでる。 |
| 明神平 大明神平とも呼ばれ、須々岐神社の奥社として祀られている。 ひのきの湯温泉から三城牧場方面へ100米ほど登ったところにある。 すすき川の本流が三つに分かれる高台で神域にぴったりである。 だから、明神平は出雲の神より昔、石器時代の自然崇拝の頃から神を祀 る場所であったような気がする。 一般に、祀る神は時代の権力によって変遷し、ときには権力者自身が神になる。 |
| 須々岐神社 須々岐水神(すすきのかわかみ)を祀る。 すすき川上流の明神平に奥社があり、ススキの葉の舟に乗って川を下った。 八龍の地に上陸し、古宮に社を設けたと伝承される。ススキの葉は川岸で擦れ片葉のススキとなって、今も神社境内に残ると言う。 貞観9年(867年)従五位下の神階を受け、祭神は建御名方命と素盞鳴命になっている。 渡来人ケルが須々岐氏の賜姓は799年であるから、須々岐神社が古宮から移って立派になったのはこの頃であろう。 |
針塚古墳 日本後記延暦18年の記事に、六世紀末、推古・舒明天皇の時代に帰化し山辺に住んだ高句麗人「ケルノマオイ」は延暦18年(799年)朝廷から「須々岐」の姓をもらったとある。ケルは更に下従五位下をもらっている。魏志に載っている高句麗の王族である。 ケルが渡来前の高句麗には「石をもって封じる」積石塚の習俗があった。 針塚古墳は積石塚でケルが住んだと思われる薄町(すすき町)地籍あり、須々岐水神社(すすき神社)がある。 一帯は北アルプスを望む景勝地。薄川(すすき川)の扇状地で、古くから稲作が発達していた。 薄町の中を大堰(おおせぎ)と呼ぶ河川が流れている。この河川が一円の稲作文化を築き豊穣の地とした。 ケルは渡来系の技術集団を率いて、大堰を築いた功績者であったと思う |
| 大堰(大柳堰) 山辺の水田地帯をうるおす川。すすき川から取水し、余水は女鳥羽川に注いでいる。築堰年代は1200年の昔、宝亀・天応年代(770-781年)頃ではないか。 この推測は、渡来系のケル氏が高度な土木技術を持っていて、朝廷の命により建設したと思われるからである。 山辺は古くから東国政策の要衝であり、やはり渡来系で朝廷支持の有力氏族、犬甘氏の支配地であった。 ケル氏の賜姓、叙位は山辺開発の功績によるものだろう。 |
南方古墳
|
 右下は銀環  横穴式石室 上方ブドウ園、下方は父母が開田で取り除いた部分。母は右下あたりに立って「ここだ」と言った。 |
山辺の地名 正倉院の白布墨書銘に「信濃国筑摩郡山家郷・・・」、天平勝宝4年(752年)とある。更に平城京の溝から出土した木簡にも同様の記載がある。 平安初期、承平年間(931〜937年)の倭名類聚鈔では「山家(也末無倍)」となっている。 江戸時代にも山家が使われていた。 |
| 束間の湯と観音さま 「湯は、なヽくりのゆ、ありまのゆ、なすのゆ、つかまのゆ、とものゆ」 と枕草子前田家本にあり、束間の湯は古くから都に知られた薬湯の一つであった。 「宇治拾遺物語」に、この湯にまつわる物語がある。 束間の湯の近くに住む男が、ある夜不思議な夢をみた。それは「明日の昼、観音さまが葦毛の馬に乗って狩着の姿で入浴にくる」とのお告げである。夜があけて、不審に思いながら人々にこの話をした。 大勢の人が集まり、湯を入れ替え、まわりを綺麗にして花を飾り、香をたいてお待ちした。 やがてお昼ころ、夢のとうりの姿の人が見えたので、皆は正夢だと、そろって拝んだ。 狩着の男は驚いて「これは何事か」と居合せる僧に尋ねた。 夢の話をすると「自分は狩で落馬し、右腕を折ったので薬湯で治すためやってきた」と言う。 尚も拝みつづける大勢の様子に困り果てた男は「どうしても観音さまと言うなら法師になろう」と、弓矢、刀をすてて、法師になったそうだ。 |
天武天皇の行宮所計画 天武天皇14年(685年)、行宮を束間の湯に造営した。 「束間の湯」は「筑摩の湯原」、山辺温泉あたりである。 造営目的は湯治の別荘のほかに東国経営のためと考えられる。古代の東山道が次第に整備され、この地が陸奥・北陸への分岐点となり、交通上の要衝として重要な位置を占めるようになった。 行幸は天武天皇の死と政変により、成就しなかった。 |
| 小笠原氏の金華山城 私の家から500米ほど登った山上に、小笠原氏の城址がある。 城主、小笠原長時は天文19年(1550年)7月15日、武田晴信の攻撃を受け敗走した。 晴信は小笠原氏の山城を直ちに破却し、平城の深志城(松本城)を拠点に信濃統治に着手した。 敗因は長時が「武道に優れているけれど我侭・自分勝手であった」「戦功の賞与を願ったら、これを罵った」と伝わっている。一方晴信は「人は石垣人は城」で信玄堤にみられるように臣下を掴んでいた。 |
| 信濃国と小笠原氏 小笠原氏は清和源氏の流れで甲斐国の武田氏と同族である。 信濃国の伊那伊賀良に入って小笠原を名乗り長清より6代松尾城を居城とした。 建武元年(1334年)小笠原信濃守貞宗が信濃国の守護職となり府中(松本)の井川に館を構え、以後6代清宗まで150年間小笠原政権の拠点とした。この間に金華山城(籠鼻城とも言う)を築いているが年代は不明確である。 金華山城を居城としたのは長朝から長時まで4代で天文19年(1550年)武田晴信に攻められ落城した。 落城の時5歳であった長時の子、貞慶は父に従い全国を流浪の後、天正10年(1582年)7月17日府中深志城に入った。 貞慶は信長に属して旧領回復をねらっていたが、天正10年6月本能寺の変で信長が没し、徳川家康の支援で小笠原家再興を果たすことができた 32年目に旧領を回復した貞慶が深志城を松本城としたのは「待つこと久しき本領」とも「伊那の松尾に対して本家筋だから」とも言われる。 その後、江戸時代の松本城主に秀政、忠真がなっている。 戦後、松本市の図書館長に末裔の小笠原さんがなり、読書会でお世話になったが市長選を元逓信大臣降旗徳弥氏と争って敗れた。 小笠原家が栄枯盛衰の激しい武家社会で連綿と家系を保ったのは鎌倉時代から弓馬兵法・作法の家柄であり、信濃の名家として幕府のほか公家筋にも深いかかわりを持っていたからである。 我が町会は金華山城の虎口方向にあり、古い図面の赤線が町割り状なので少なからず関わりがあったと思う。 |
| 山家城 鎌倉時代の末、神(諏訪)氏が築城。文明年間(1469−86年)末頃、小笠原氏の分流、折野薩摩守昌治が伊那より移り、山家氏を称して改築したといわれる。 小笠原氏が金華山城に入ってからは、背後を守る要害城として重要視された。 |
| 桐原城 この地の有力な土豪犬甘氏の分派、桐原氏の山城である。桐原氏は小笠原氏が伊那の松尾から府中(松本の旧名)に入封すると小笠原氏に属した。金華山城の支城として、薄川をはさんだ向かい側の山上に構築された。 天文19年(1550年)小笠原長時が武田氏に敗れ、城をすてたとき桐原城に逃れている。長時は諸国の大名を頼って全国を流浪したが桐原氏は最後まで長時に従った。 32年後、天正10年(1582年)長時の子貞慶が旧領を回復し松本城主となり桐原氏も旧地に復興した。 |
| 水番城 金華山城の飲用水は、1.5キロほど離れた沢から引かれた。水路は二つの尾根を巻いて、ゆるい勾配になっている。おそらく木管を用いたであろう 水番城はその途中の尾根にあり、水番と金華山城の後方を見張る役目をもっていたと思われる。 |
| 宮原城 水番城から更に二つ奥の尾根上にあり、山家城、桐原城を見通す位置にある。山家城とは薄川をはさんで、金華山城の後方を守る城である。 |
| 徳運寺と廃仏毀釈 徳運寺の元は、徳雲寺で山城国宇治の平等院の末寺であった。 開山は真言禅師、すなわち雪村友梅である。友梅は元に渡り23年の修行を積み、元帝から「宝覚真空禅師」の号を賜った高僧である。 元弘元年(1331年)山辺谷を領有し山家氏を名乗っていた神為朝の懇請 を受け徳雲寺を開いた。 明治維新で松本藩は明治3年 (1870年)8月明治新政府から、仏葬から神葬にする許可を得た。藩の政策は神仏分離にとどまらず、廃仏毀釈運動にまですすんだ。 翌年には藩内の村々のほとんどが神葬祭に変わった。無檀家となった寺の僧侶に帰農をすすめ、松本藩のうち筑摩群下の78ヶ寺の中48ヶ寺(62%)が帰農した。 徳運寺は明治4年11月帰農願いを松本県に出して帰農した。 ところで松本県の時代は明治4年7月14日から同年11月20日までの4ヶ月で筑摩県に合併した。 廃仏毀釈政策は筑摩県合併で明治4年末には終わりを告げ、寺院の復興、檀家はもとの仏葬にもどる者が多かった。 1年ほどの間に多くの文化財を消失した廃仏毀釈の嵐は、松本藩がことさら激しかった。それは藩主戸田光則が水戸学の信奉者であった上、徳川家康の義妹を正室とした康長以来徳川の旧姓、松平と三つ葉葵の紋章を許された家系だったからである。 幕末期までの幕臣が明治新政府に好印象をもってもらうためである。 徳運寺はその後まもなく、私の祖母の祖父にあたる佐々木貫法和尚が再興した。 |
| やまべの灯り 山辺に灯りがついたのは明治32年(1899年)12月8日、松本電灯株式会社がすすき川に舟付発電所を建設した。 取り入れ口から導水路を流し、標高差を利用したクリ−ンなエネルギ−である。 その後、上流に三つの発電所ができているが、発電所の鉄管以外ほとんど景観に違和感がない。 平成11年が、舟付発電所の建設100周年。松本出身の中部電力社長 も来て祝賀会をやった。 舟付発電所の水車は米国製、最新式で510馬力であった。 電気料、器具貸し賃を合わせ10燭光、1ヶ月料金が80銭であった。 第二発電所 明治42年7月に建設され、米国製の発電機、ドイツ製の水車・導水管が使われた。周波数は60ヘルツを採用した。 第三発電所 大正7年に建設された。 |
金華山の地下工場 昭和20年(1945年)2月、金華山地下に工場建設が始まった。戦闘機の「零戦」など製造していた三菱名古屋航空機製作所が疎開するためであった。 地下工場では「零戦」の後継機、「烈風」の月産20機を目標にしたといわれる。 6ヶ月後の20年8月敗戦で、建設が中止となり、今は入り口がひとつだけ残っている。 中国人捕虜や朝鮮人労働者の虐待・強制労働があった。 |
| TOP | ペ−ジ先頭 |