| TOP | 山辺ぶどう | 山麓の民俗 | 先人のメッセ−ジ | 森の現況 | エコツ−リズム | グリ−ンツ−リズム | |
| エコマップ |
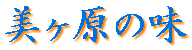 空気 がうまい 水 がうまい だから料理 がおいしい |
| おふくろの味 | 古里の味 | 山の幸 | 川の恵み |
| エコクッキング |
| 凍り餅 |
| ||
| あられ | 薄めに延ばした餅を1センチ角ほどに切り、乾燥させたもの。長期保存ができる。フライパンで炒り砂糖醤油を絡ませて食べる。 | ||
| 草もち | 花見、桃の節句、春祭りなどにモチ草(ヨモギ)を入れた餅をつく。ちぎって丸め、砂糖をまぜたきな粉をまぶしたり、あずき餡を入れて饅頭にする。残りは延して切り餅にする。モチ草の香りと緑が、信州の長い冬からの開放を告げる。 | ||
| そば | テレビのそば道場などで、漠然と分かっていても最初はうまく出来ない。 教わりながら経験を積むより仕方ない。練るときの水回しがよければきれいに伸びる。最も素朴で贅沢な食べもの。我が家では標高1000〜1400米産のそば粉を用い、40年近い経験の女房が打つ。 とうじそば かけそば、天ぷらそばは一般的だが一度食べると病みつきになるのがとうじそば。ゆでたそばを小さな玉にしておく。具の入った味噌汁や醤油汁の煮立った中へ一玉づつとうじ籠に入れてとうじる。椀にあけ具をのせ汁をかけて食べる。七味唐辛子・きざみ葱がよく合う。キジガラのだしで具にキジ肉、干わらび、凍み豆腐となればおふくろの味そのものである。 | ||
| 漬物 | 野沢菜 信州の漬物代表。炬燵にあたり、漬菜でお茶を飲み語り合う姿は信州の文化である。晩秋に漬けこみ、気温の低い信州ならではの味である。春の暖かさで酸味のでる頃の味も格別だがそれまでが旬である。 大根 米ぬかに干し柿で剥いた皮、ナスの葉を乾燥し、混ぜ合わせて漬ける。 翌年夏まで日もちのする硬大根と、時漬けの柔大根がある。 味噌漬 ナス・瓜・ごぼう・大根など信州味噌の味は好まれる。みょうがの花・芹は風味と歯ざわりがよく刻んでお茶漬けは最高である。 カス漬 酒粕で本瓜を漬ける。近年はセロリも漬けられるようになった。 梅漬 梅と紫蘇の葉の塩漬け。砂糖をかけてお茶うけにする。毎日ひとつずつ食べれば血液を弱アルカリ性にする健康食品と言われる。 | ||
| 干し柿 | 渋柿を剥き、吊るして干す。頃合をみて藁の上に並べ、表面に糖分が乾燥した白い粉の吹くのを待つ。 | ||
| ほう葉の味 | 我が家には樹齢70年近い「ほうの木」がある。 ほう葉巻き 6月、月遅れ端午の節句にかしわ餅と同じにほう葉巻きをつくる。ほう葉の香りがさわやかである。 ほう葉味噌 みりん・椎茸・コンブ・鰹節のダシ汁を加えて練った信州味噌をほう葉に延ばし、炭火で焼く。ご飯にのせてお茶漬け。おにぎりに塗って焼きおにぎりも良い。 | ||
| 鉄火味噌 | 大豆やナスに信州味噌を加えて炒める。砂糖・みりん・だし汁・ショウガ・七味唐辛子・ごま油で味付けする。 | ||
| フキ | フキ味噌
あく抜きして刻み三杯酢をかける。砂糖少々で苦味がやわらぐ。 キャラブキ 野ブキを皮つきのまま米のとぎ汁で硬ゆで、流水で半日あく抜きする。3センチほどに切り、醤油・みりん・酒・調味料に水を加え弱火で汁の無くなるまで煮る。火をとめて一晩おき、再び醤油・みりんを入れて煮こむ。長期保存がきく惣菜である。 フキと身欠きニシンの煮物 キャラブキと同じにあく抜きした野ブキを、流水でもどした身欠きニシンと味噌味の煮物にする。山国信州の田植え時季の味である。 フキの葉のつくだ煮 フキの葉をさっと茹で、流水で2日間苦味をとる。細かく刻んで醤油・砂糖・酒にだし汁を加え煮つめる。 | ||
| ニシンの 昆布巻き |
魚貝類は山の信州へ乾物や塩づけで運ばれた。年越魚も塩ブリや塩サケで山を越し、今もブリ街道の俗称が残っている。百姓にとって一番大変な田植えのとき欠かせない料理がニシンの昆布巻き。山の神を田の神として迎え祝いの「晴れ料理」である。乾物の身欠きニシンはうまみが一段と増している。 | ||
| オシタシ (おひたし) |
雪が消えて間もない田圃で摘んだナズナのオシタシには長い冬からの開放感がある。 畑の畦のミツバゼリは歯ざわりと香りがよい。 オコゲ とげがあって畑の垣根にしてあるオコゲの幼葉をオシタシにする。時季を失うと1年待たなくては食べられない。独特の風味、ギュギュと歯への感触がよい。 コウレン葉(オオバギボウシ) 地方によってウリッパと呼ばれるように緑があざやかでシャキっとしている根元の白いところはぬらめきがあってソフトな味である。オシタシのほか煮つけ、油いためもよい。 | ||
| 焼きナス | ナスを丸ごと灰につっこんで焼く。灰を払って引きさき、おろし生姜に醤油をかけて食べる。包丁を入れ味噌をはさんでもよい。 | ||
| カボチャだんご | 小豆あんしるこの中にカボチャと小麦粉だんごを入れて食べる。冬至の定番料理で風邪にかからないと言う。 | ||
| ゼンマイと油揚げの煮つけ | ゼンマイやワラビは油揚げと相性がよく鄙びた味がする。コゴミと油揚げも同じ。 | ||
| 塩イカの キュウリもみ |
山国信州では煮イカの塩漬けが売られている。きざんだキュウリに流水で塩抜きしたイカにを加え揉むと適度な塩気の料理になる。 | ||
| イナゴのつくだ煮 | 醤油・酒・砂糖・みりんで煮つける。 | ||
| 甘酒 | 蒸らしたご飯に米こうじをまぜ、炬燵の隅に一晩おいてできあがる。 | ||
| ぶどうジュ−ス | 切り取ったぶどうを軸毎かめにあける。砂糖を入れ粒をつぶす。毎日かきまわし一週間ねかせてしぼる。壜にうつし煮沸滅菌する。果汁100パ−セントの栄養と味。 | ||
| ぶどうジャム | ぶどうジュ−スを搾った残りかすの軸と種を取り除き煮詰める。煮沸滅菌して保存できる。 | ||
| カリンの砂糖漬 | 薄切りにしたカリンを塩水であく抜きし、広口の壜に同量の氷砂糖と入れる。カリンはお茶うけに、汁は咳止めにきく。 | ||
| ぶどうの 紫蘇巻き漬 |
ぶどうは巨峰がよい。紫蘇の葉で巻き、広口の壜に同量の氷砂糖と入れる。 |
| ペ−ジ先頭 |
| 山辺ぶどう | 美ヶ原の山麓、やまべ地区はぶどう産地として古い歴史を持っている。 標高が高く、昼夜の温度差がはげしいので他では真似の出来ない色づきとなる。特にデラウエアやナイヤガラは産地が少ない品である。 |
| 山辺りんご | 果樹は土質によって味が違う。砂礫質で水の排水性がよく、かつ保水性があると根張りが健全な樹木となる。山辺りんごは美ヶ原山麓の扇状地に栽培されるサンふじと呼ばれる無袋栽培の「ふじ林檎」である。袋かけをしないので太陽を一杯あび真っ赤なりんごになる。よく熟したりんごを二つに切ると中心部分がハ−ト型に黄みを帯びている。百姓は「蜜がのってきた」と言い、酸味と甘味のころあいが良い状態である。 |
| 清流米こしひかり | 美ヶ原を源とするすすき川は松本市内を流れる河川のうちで最も清らかな流れである。その両岸の水田は「こしひかり」栽培の限界、標高750米に達し、砂礫土ですすき川の水で育つ。 |
| 蜂蜜 | 花の種類によって蜜の味が違う。最近口に出来ないレンゲ草の蜜は味、香りともよかった。アカシヤもうまい。栗は香りが鼻につく。純粋の蜜は冬は固まって白くなりザラサラした舌触りになる。 |
| 蜂の子 | 昭和天皇は美ヶ原山麓の霞山荘にお泊りの際、蜂の子の甘露煮を召し上がった。 爾来、その味を愛でられ霞山荘では毎年献上していたそうである。 |
| ジンギスカン鍋 | 羊肉(マトン)焼き。今では袋入り市販品が味わえる。戦後肉不足のとき、やぎやひつじの肉をすき焼きにした。独特の鼻につく匂いがあった。昭和25年ころ、どこから製法が由来したか三城牧場からジンギスカン鍋が広がった。小羊のラムはやわらかでおいしい。 タレは醤油・砂糖・ニンニク・玉ネギ・リンゴ・にんじん・大根・コショウ・七味唐辛子・ごまをすりつぶし混ぜ合わせてつくり、マトンを2時間ほど漬けこむ。 |
| ペ−ジ先頭 |
| きのこ | 天然きのこで判別できるのは松茸、リコ−ボ−、アミ茸、ウシビテ、栗茸、紫シメジ、黄シメジ、ヤマドリイグチ、ニギリタケ、カラス茸、ネズミアシ、アカンボ−程度である。図鑑でも類似のものが多く口にする自信がない。 栽培ものでは椎茸、舞茸、ナメコ、シメジなどがある。 |
| 山菜 | ワラビ ホウロウ引きの器に木灰を降り、一握りほどに束ねたワラビを並べる。全体に木灰を降り、またワラビ木灰をくりかえす。押しぶたして熱湯をふたがかくれるまで注ぎ5時間ほどおく。水洗いして茹で流水にさらしてアクを抜く。 タラの芽 天ぷら、汁の実、味噌あえ、煮つけのどれも味、歯ざわりがたのしい。「山菜の王様」とされるが、コシアブラに軍配をあげる人もある。タラは芽が開いてトゲが痛くなっても天ぷらになり食感がよい。 ウド 葉先は天ぷら。アクを抜いて煮物がよい。栽培ものよりアクが強く、それが山ウドのウマミである。強く塩漬すると緑のままに保存される。 コゴミ、ゼンマイ おひたし、煮物。 ウトブキ 煮物。 山ブドウの芽、たんぽぽ 天ぷら。 |
| 山ぶどう | 道路端の林縁に沢山みられるが、雌雄意株で良い房状になるのは珍しい。高級ワインの原料になる。 |
| サルナシ | 奥山にのみ見られる。最上級のワイン原料になる。 |
| 朝鮮五味子 | 五味子は五つの美味とのこと。焼酎で果実酒にする。 |
| ぺ−ジ先頭 |
| イワナ | すすき川に本来棲む。渓流釣りで先行者がいると後は釣れない。敏感である。水面に人影を落とさないようにして釣る。塩焼きがおいしい。火であぶり囲炉裏の煙をかけながら乾燥したものを焼戻し醤油をかけて食べれば最高。 |
| ヤマメ | すすき川に放流されている。イワナより更に敏感。餌を完全に流れに合わせ、食った瞬間を逃すと生餌も吐き出される。脂肪分が多く味も一段と良い。 |
| ニジマス | すすき川に放流されている。釣りやすい。イワナ、ヤマメより味は落ちるが形が大きくなり燻製に適す。 |
| TOP | ペ−ジ先頭 |