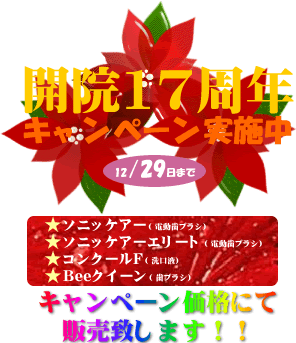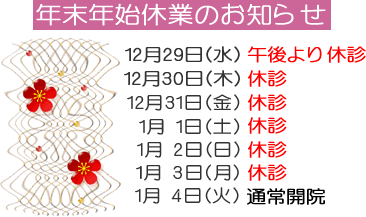朝起きるのが辛ーい(>_<)季節になりましたね。
そんな寒い季節にぴったりの体が温まるお料理をご紹介します。 |
 |
| :材料: |
|
・豚バラ肉・・2枚
・かぶ・・・・3個
・玉ねぎ・・・1個
・にんじん・・1本
・オリーブオイル・・大2 |
A クリームソース
・バター・・大2
・薄力粉・・大3
・牛乳・・・2カップ
・コンソメスープ・・3カップ
・塩・こしょう・・・各小1/2 |
|
:作り方:
①:たまねぎ・にんじん・かぶは食べやすい大きさに切って、耐熱皿に入れてラップをする。
電子レンジで約3分加熱する。
②:鍋でオリーブオイルを加熱して一口大に切ったバラ肉を入れて焼き、①の野菜を加えて炒める。
③:②にAのクリームソースの材料を入れて、粉っぽさがなくなるまでよく混ぜながら煮詰める。 |
| ☆電子レンジを使って野菜を軟らかくするので、時間が短縮され簡単に出来ますよ!!☆ |
| 担当:宮崎 香代子 |