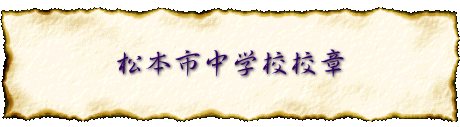清水中学校
松に純白の蓮華をあしらい、その中央に中学の「中」の字を入れてある。松は松本の松をとり、色変えぬ松の緑、希望、永続性をあらわし、蓮華には濁りにしまぬ若人の清浄の意を込めてある。
鎌田中学校


三つのしらかばの若葉を組み合わせたもので、昭和22年9月3日、本校開校の年に制定された。しらかばの白さは、清純さと雄々しい心を表し、三つに組んだ若葉は、協力と友情を表しているといわれる。校歌にも、「さればすがしき白樺の、三つに組みたるうら若葉、かざす誇りを貫かん、われらの鎌田中学校」という一節がある。

丸ノ内中学校
一 雪のマークは蛍雪の功を表現し勤勉を象徴(松本の松ではない)。
二 円は円満を表現し円満な人格のへの完成を目ざすことを象徴。
三 円の仲の「中」は丸ノ内中学を象徴。
制定 昭和二十五年二月 校長 桐原 与喜一 先生
考察 太田 正重 教諭

旭町中学校
昭和23年制定。旭日(昇って間もない太陽)をデザインしたもの。旭日は未来の日本を背負って立とうとする旭町中学校の生徒の強い勇気と高い理想を表している。

「若松」は松本市立の中学校という意味と松が古来尊ばれてきた、節操・ 強靱の象徴として描かれている。「山」は校舎3階から眺められる日本アルプスを表している。それらを三方にはりだすことによってパランスのとれた人間形成である「真・善・美」等の三位一体の気持ちをこめている。
信明中学校

松島中学校
松島中学校の前身島内中学校が設立された昭和22年の終わりには、この校章の図案が考えられていたようである。当時の教諭青柳司郎先生が、建学のシンボルとしての高山植物「つくも草」をもとに、汚れない純黄の花弁、若さを表す緑の葉を配し、情熱を表す赤で「中」の文字を描いた。松島中学校十周年となる昭和42年に、校旗の制定に合わせて図案の見直しが行われ、洗練された現在の校章となった。

「真・善・美」の3つの精神的な意味合いを持たせた仁能田のやまをモチーフにしており、それらの三角形に「飛翔」、「向上」の意を込めて、すべて上向きに空間を持たせて配置することにより、学校がこれから高い理想を持って発展し、伸びていこうとする姿があらわされている。
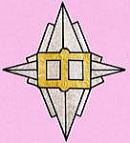
山辺中学校
昭和30年(1955年)、入山辺里山辺両地区より募集し、山辺中学校の新保幸一氏に決定した。 山辺の『山』と朝に夕に仰ぐ気高くゆるぎなきアルプスの峨々たる山脈を形どって『中』の字を囲んだもので、この学び舎に学ぶ若人たちのき然とした精神を鋭く表現したものである。

高綱中学校

菅野中学校

筑摩野中学校

明善中学校

女鳥羽中学校

鉢盛中学校


会田中学校
梓川中学校

雄々しくそびえるアルプスをかたどり、「中」を囲んでいるのは松の葉を組み合わせたもので、松林の中にある中学を表している。この精神は、天空にそびえるアルプスに、波田中健児の心の広さと、どんなことにもくじけない力強さや粘り強さを表し、松の緑には真理探究の願いが込められている。 (昭和22年、当時2年生の春宮雄剛君・古畑多美子さんの案により制定。当時の中学校は現在の波田小学校敷地内に置かれていた)

波田中学校
昭和42年安曇中学校と稲核中学校が統合され、それに伴って昭和43年度に校歌とともに制定された。輪郭の円は「安曇」の「安」を図案化したもので、平和を表し、三つの頂点は北アルプスの山岳を象徴すると共に本校で大切にしてきた、知育・徳育・体育を表現している。
安曇中学校

大野川中学校
乗鞍岳と御池に映るすぐれた郷土の自然を表す。 雄大で心豊かな人への願いがある。和田清「校章の自然誌」信濃毎日新聞社昭和60年6月20日発行から引用

昭和33年度制定。外郭は乗鞍岳であり、山頂に白雪を受けた状態を表し、奈川の頭文字を片仮名の「ナ」になるように美的な感覚を重視してまとめたものである。当時の職員の折井 久氏の図案による。
奈川中学校